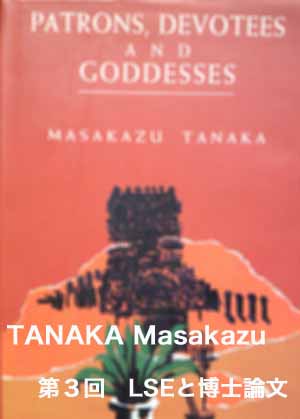
第3回目は「LSEと博士論文」というタイトルでお届けします。LSEとは、The London School of Economics and Political Scienceの略称です(タイトルの画像は、田中先生が英語で出版された博士論文です)。今回は、長期の調査のあとどのような経緯で博士論文を執筆されたのかについてお話いただきました。ジンカン文化人類学分野でおこなわれている博士論文予備ゼミの原型となる、LSEのwriting up seminarがどのようなものであったのかを垣間みることができます。
*このインタビュー記事は、書きおこし原稿をもとに、院生とホームページ担当者が編集しました。事実関係については先生に確認していただきましたが、タイトル、構成などは担当者の責任のもとに編集しています。
(インタビュー第2回へ)
院生:
復学してからは博論執筆に集中されていたのでしょうか?
Friday Seminar
田中:
調査から戻ると、すでに触れたWriting Up Seminarに参加することになります。ここで旧友や新しい仲間と再会する。金曜日の朝はFriday Seminarというのがあり、これは学科の教員全員に開かれているセミナーで、大学院生から国内外の研究者まで最新の発表が聞かれるゼミです。京都人類学研究会を毎週やっているようなものです。学期ごとの担当者が決まっていて、共通テーマが決まっていることもあります。担当の期間は1学期なので10回と短い。参加者が固定されているわけではない。ですから、日本の共同研究とも違う。Death and Regeneration of LifeとかMoney and the Morality of Exchangeなどは、こうしたゼミから生まれています。後者は私がフィールドから戻る直前の1983年10月から始まって、私も参加しました。
Friday Seminarではギアツやデュモンも発表していましたね。ハックスレー賞の受賞が決まって渡英された伊谷純一郎先生(注1)も発表していました。先生は、授賞式での講演と、このFriday Seminarの両方でお話をされました。
すでに説明しましたが、Writing Up Seminarは担当の先生が一人、あとは院生たちです。事前に博論の章を参加者に配布しておき、討議をするというきわめて有用なゼミでした。ロンドン大のほかの人類学科にはこのような形式のゼミはやられていなかったと記憶しています。フィールド調査の後各自論文執筆に取りかかると、「孤独死」状態になりかねない。そんな院生たちが、こうやって定期的に集まって自分の専門でもない論文を読み、しかも有益なコメントをするようにいろいろ考えなければならない。これはよい刺激になりますし、たいへん鍛えられます。お互いの執筆ペースも分かります。当時は調査が終わってから3年以内に出すことが期待されていました。それ以上だといつになるかわからなくなる。私は、1986年3月に2年半くらいで提出していますが、当時の学生たちも私とほぼ同じころ(1986年―87年)に博論を出していますから、このセミナーの効果は大だったと思います。2週間ほど前に1章分のドラフトが配られていて、当日ディスカッションする。事前にテクストが読めるのも助かります。こういう形式はべつに博論でなくてもいいわけですよね。
院生:
先生もそこで発表されたりしましたか?
田中:
私もWriting Up Seminarで3回ほど発表しました。最初の発表のとき、モーリス(ブロック)が開口一番Masa’s paper struck meと言ってくれました。セミナーの終わったあとでまた同じパブでビールを飲んでいるときもみんな喜んでくれていました。心配していたよりはましだったのでこんなに喜んでくれるのかなとも思いましたが、そういう心遣いをするタイプではなかったし、こういうゼミで礼を言われることもまれですから、たぶん内容がほんとに評価されたのだと思います。モーリスから聞いたのでしょう。あとでジョニーやクリス(・フラー)からも「ゼミ発表はうまく行ったんだって?」というようなことを言われました。
イギリスと日本のゼミを比較する
院生:
このWriting Up Seminarは、京都大学の博論予備ゼミみたいなものでしょうか?
田中:
そうです。ただし、うちは年2回で、しかもひとり1回限りだけど、LSEでは毎週か隔週でやっていた。
院生:
結構な頻度でやってたんですね。
田中:
LSEの場合は、先生は担当の先生しか出てこない。だから京大の文化人類学でやっている博論ゼミとも違う。LSEでは各教員がそれぞれゼミをもっているわけではないから(注2)、院生が参加するゼミはフィールドワーク前の技術指導的なゼミ(カメラの使い方とかインタビューの仕方など、すごく基本的なものです)ゼミとフィールドワークの後に参加するこのWriting Up Seminar、それから学科全体のFriday Seminarの3つしかない。だから院生たちが集まるという意味で、Writing Up Seminarは京大の普通のゼミに近い。ここにフィールドから戻ってきた博士論文を書いている最中の院生が参加することになっている。京大でも似たようなことをしているけれども、ひとり1回限りですよね。博論ゼミに至るまでの章ごとの発表は個人指導とか、教員ごとのゼミでやりましょうっていうことになっている。
院生:
じゃあ、南アジア関係でかつてやっていた博論ゼミ(注3)はどちらですか?
田中:
南アジアの方がもっとLSEのゼミに近かったかもしれない。
院生:
それは、LSEをモデルにしたんですか?先生が始められた?
田中:
そう。もちろん南アジアの方は、ここの文化人類学と違って回数も多かったし横断的にやった。ASAFAS(アジア・アフリカ地域研究研究科)の教員と学生も来ていたし、学外だと民博(総合研究大学院大学)の人も来ていたし、立命館大学の学生もいた。名前は博論ゼミだけど、実際は修論を書いている人も発表していた。だから、あのゼミがあったからなんとか博論が書けましたという人も何人かいて評判はよかった。私と足立(明)さん、田辺(明生)さん、と3人くらいで、宮本万里さんや石坂晋也くんに事務をしてもらっていた。あとで藤倉(達郎)さんも参加した。
院生:
LSEには自主ゼミとかはありましたか?
田中:
僕らは南アジア関連で2つやりました。1つは、博論を書き始めた南アジア専攻の学生たちと、1985年の夏だと思いますが、こないだ民博が招いたクリス・ペニーの自宅で何度か会合をもちました。スリランカにあるアヌラーダプーラという仏教聖地の調査をしたエリザベス・ニッサンLiz Nissanさん、インド映画を博論で取り上げていたRosie Thomasも。彼女はすでにどこかのカレッジで教えていました。夏休み中なんかに週1回集まって、博論の一部のドラフトを持ちよって議論する。昼にはクリスたちが作ったカボチャスープなんかをいただく。もうひとつは、スリランカの研究者のセミナー。これはスティラット先生もいたので、もうすこしフォーマルな感じもしました。何度かサセックス大学まで行きました。

LSE Old Building入口
記念講演会
田中:
それから、直接大学と関係ないけど、講演が多かったですね。いわゆるMemorial Lectureというやつで、例えばマリノフスキーとかフレーザーの名前がついている講演会がたくさんある。そういうところでリーチとか著名な研究者がしゃべるわけ。それは学生にとって大きい影響を与えていたと思う。日本ではあんまりやらないじゃない。学会で記念講演はやるけれども、誰々先生を記念してやるっていう講演会ってあまりない。伊谷先生の話が出たけど、そのハックスレー賞受賞のときに講演会をする。デュモンとかギアツとかがわざわざ来て話をするわけです。LSEが直接関与していたのはマリノフスキー記念講演会です。それは40歳前後の人が対象だったから、私が留学していたころは、インゴルドTim Ingold(注4)、キース・ハートKeith Hart(注5)、スペルベルDan Sperber(注6)、ジョニーやジョック(スティラット)がLSEのOld Theatreでしゃべっていました(注7)。インゴルドのときはジーン・ラ・フォンテーヌ教授が司会。スペルベルのときはモーリスだった。そのあと5階のシニア・コモンルームでワインとサンドイッチのパーティーがある。福井勝義さんとはじめてお話ししたのもインゴルドのマリノフスキー記念講演会の後のパーティーの席上でした。こういう講演会は最先端の研究を披露するわけだから刺激になるよね。リーチなんかも私が滞在中にロンドンで3回くらい講演をしていますが、活字にはなってないのではないかな。マリノフスキー記念講演のなかでもっとも論争を引き起こしたのが第1回講演だったリーチ(注8)のRethinking Anthropologyでした。これは翻訳されて『人類学再考(注9)』という同名の書物に収められています。その次は1976年のモーリスの時間についての講演The Past and the Present in the Presentです。マリノフスキー記念講演のベスト10くらいを集めて訳し、それらに関係する論争を紹介したらおもしろいと思ってすこしは考えましたけどね。
院生:
日本では受賞記念講演とかはやらないですもんね。学会賞とかとったとしても。
田中:
ほとんどそういう機会ないよね。人の名前をつけているのだってほとんどない。京大だったら、伊谷純一郎記念講演会みたいなのを毎年やったらいい。伊谷さんの業績に関係するような研究をした人に賞を与えると同時に講演してもらう。南方熊楠賞というのがそれに近いけど、本当はもっとあってもいい。

LSEのcrest
パソコンルーム
院生:
話は変わりますが、博論を書いていてスランプとかはありましたか?
田中:
あんまり、そういうのはなかった。今もないですね。
博論執筆の話はほぼしてしまったけど、印象に残っていることをもうひとつ話しておきます。私が書き始めたのはたぶん84年になってから。スリランカからロンドンに戻ったのは1983年11月です。その頃にはもうパソコンが入っていた。だから、博論執筆は最初からパソコンでやっていた。それまでのレポートはタイプでしていたけれどね。最初はBBCとかいうパソコンが3、4台狭い部屋に置いてあった。当初は小さな部屋だったけど、需要も増えたのか、大きな部屋が用意されてそちらで博論を書くことになった。LSEのいいところは、経済学が中心で(ロンドン大学全体から見るとLSEは経済学部という位置づけです)、政界とのコネも強くお金もあったこと。それでコンピュータ関係の施設もしっかりしていた。さらに1部屋増えて各部屋に2~30台IBMのパソコンが置いてあって、24時間自由に使えた。書く環境は他のところに比べればずっとよかったです。だから書き始めた人たちはLSEのPC部屋にずっといることになる。これもまたよかったと思います。ゼミでだけでなく、パソコンのある部屋ででも一日中一緒にいるわけです。京大の院生室のようなもんですよね。LSEの学生全員に開かれていましたので、ここで仲良くなった他学部の院生もいます。この部屋には共有のプリンタがありましたが、博論の清書用には不十分でした。でも、コンピュータ関係の先生が自分の部屋のレーザープリンターを真夜中に使わせてくれた。ほとんど見ず知らずの先生が使わせてくれるわけです。パソコンの使い方が分からない人たちのために、技官の人もいつも引っ張りだこでした。みんな親切なひとたちでした。真夜中も使えるというのはほんとによかった。とくに文系しかないところは閉まっちゃう。
博士論文執筆の最後は籠ってやりたいところですが、自宅にPCなんて持てない時代でした。自宅で執筆はできない。本や論文は自宅で読めるけど、執筆は基本的に大学のパソコンルームでしなければならない。夜は静かでいいですよね。LSEは街中にあって、オペラハウスのあるコベントガーデンなんかすぐ近くでした。少し歩けばピカデリーサーカス。夜11時ころ、ロンドンの繁華街を横切ってソーホーの中華街まで歩いて夕食をとって帰宅するわけです。閉店間際だと残り物しかなくて安くなっている。毎日中華でだんだん太ってきた。最後のふた月くらいはずっとジャージ(紺のトレパン)で通していたと思う。ゴム紐のはいったジャージ。実際は部屋着というかパジャマなわけです。当時、昼間からジャージなんかはいている人はロンドンにいなかったと思う。
ロンドンの中心街から郊外に一晩中走っているナイトバスっていうのがあったから、真夜中すぎてもいつでも帰れる。そういうバスには、ディスコで遊んだ酔っぱらいの若い連中がこれから帰宅しようとしていっぱい乗っている。大学に一晩中いて、朝早く帰ることもあったけど、それはそれで面白かった。朝早く自宅からバスに乗ってLSEのあるビジネス街にやってくるのはみんな掃除人たち。カリブ系の黒人女性たち。彼女たちは朝一番で六時頃オフィスが始まる前に来て、ホワイトカラーが出勤する8時までにビルの掃除をするわけです。真夜中だと、遊んでいる連中と一緒に帰って、朝までいると、働きに来る女性たちとバス停で会うことになる。LSEにはキャンパスはなかったけど(屋外でゆっくりできるのは屋上くらい)、ロンドンのいろんな一面が見られたのはよかったと思います。
博論審査viva
院生:
博論を出すタイミングはありましたか?
田中:
私の場合は就職の話しも出ていたけど、博論執筆と直接関係はしなかった。当時は公募ではなかったので、ひたすら待っているという感じでした。スリランカでフィールドをやっていた時にも就職の話があってコロンボの病院に健康診断を受けに行ったりしました。これは結局決まりませんでした。だけど、博論を書き終えるころには非公式に3つもオファーがあった。今だと信じられない話ですよね。3番目が民博からでしたが、採用時期が1986年8月1日で一番早かった。南アジアをもう少し強力にしたいということでした。それで3月か4月に一度発表を聴いてもらおうということになっていた。
もう一つは、こっちのほうが大事だったのですが、妻は一足先に帰国している。3月10日に最初の子供が生まれる予定だった。それまでには博士論文を書き上げて日本に帰ることにしていたのですが、すこしはやく生まれた。2月27日です。それで博論提出は間に合わなくてずるずると延びて3月終わりくらいに書き終えて一時帰国をした。製本とかはエリック・ハーシュに頼んで、代わりに大学に出してもらった。そしてまた、審査のためにロンドンに戻るわけです。
院生:
3月に戻って、生まれたばかりの赤ちゃんの顔を見て、民博で面接をして、そしてロンドンに戻ったのですね。
田中:
そうです。イギリスの審査はvivaと言って、インフォーマルな感じでした。今の京大みたいにパワーポイントを使う発表もないから、用意することもない(すくなくとも私は思いつかなかった)。それで前々日の真夜中にベーカー街の映画館のレイト・ショーでやっていた『マドンナのスーザンを探して』を見に行った。ピーター・ガウ(第1回インタビュー参照)が最高の映画だと、ほめていたので1人で見に行った。そんなもんです。
イギリスは他の大学もそうだと思うけど、1人は同じロンドン大学から、もう1人は他の大学から。審査員は2人だけなんです。指導教員は審査に加わらないし、参加もできない。院生はふたりの審査員と向き合って質問に答えるわけです。
院生:
えっ、指導教員は入れないんですか!
田中:
入れない。審査員は指導教員が選ぶんだけどね。一番研究内容が近かったということで1人はモーリス・ブロック。もう1人はジョナサン・パリーの先生だったエドマンド・リーチ。
院生:
モーリスとリーチが博論審査員ですか。どちらも大家のおふたりですか。
田中:
そうなんだよ。2人とも論争を引き起こしたマリノフスキー記念講演の大御所です。リーチはナイトの称号をもっていた数少ない人類学者の1人。サー・エドマンド。審査員が決まって、周囲の人たちに言うとさ、モーリスはいいとして、リーチについてはみんなが同情するっていう感じだったな。「あの人、大丈夫か!?」みたいな。
6月23日にモーリスの研究室で審査をやった。リーチもケンブリッジからやってきた。かれは当時すでに皮膚がんを患っていて大きな絆創膏を額に貼っていました。ここはどうなっているのかとか、はじめはふつうに質問するのだけど、リーチはモーリスに何か言いたいんだよね。「この博論に書いてあるヒンドゥー教のことをなにか知っているか?」みたいなことを私ではなくモーリスに聞くわけです。だから、そのうち、リーチとモーリスお互いがやり合い始める。やり合いと言ってもリーチのほうが大先生ですから、モーリスはどちらかというとおとなしく聞いていて、「ヒンドゥー教は日本の宗教に似ている」などと、リーチには判断できないようなコメントをしたりしている。だから私自身の博論の内容についてはそんな厳しいことを言われなくてよかった。モーリスは言いたいことも言えず、欲求不満になったのか、帰り際、「今度は2人だけで会って続けよう」と言われたのを覚えています。リーチが審査員に決まって、一番嫌だったのはモーリスかもしれません。私自身の博論についてはおふたりがなにをコメントしたのかほとんど覚えていません。もったいないと言えばもったいないことです。
みなさんもそうですが、博論審査は、学生生活のクライマックスでもあるわけですよね。でもその日はもうひとつのクライマックスがありました。それは就職の内定です。
審査の当日は民博の内定が決まる日だったんですね。時差が8時間くらいあるから、審査が始まる時にはもう内定結果がわかっていた。審査の前にたまたま事務室でモーリスにあったから、もう採用されたと一言伝えプレッシャーをかけておいた。
まあそれで、審査は2時間くらいで、終わったあとは何人かで大学のパブでビールを飲んだ。クリスティーナ(トーレン)から「なんで審査のことを言ってくれなかったの?言ってくれていたらお祝いしたのに」と言われましたが、あまり大々的に祝ったりする雰囲気ではありませんでした。ジェルの学生だったスザンヌ(Susanne Kuechler)の審査の時は、モーリスとマリリン・ストラザーン(注10)が審査員だった。たまたま、審査の直後に彼の部屋に行ったので彼女に挨拶をしたことがありますが、そのときもとくになにかあったわけではありません。ストラザーンもすぐに帰りました。
帰国直前にたまたまジェルと一緒になってホルボーンという地下鉄の駅まで一緒だった。そのときかれが「博論は出版できそうじゃないか」と言ってくれましたから、内容は悪くはなかったと思います。結局この博論は供犠についての議論を外して、まず人文研から、そのあと修正版をマノーハルというニューデリーの出版社からタイトルを変えて出版されます。英語で出したので反応も多く、書評もいくつか出ました。論文も大事ですが、みなさんも早く英語で本を出すことをお勧めします。
授与式には出ませんでしたが、博論をすこし修正し、正式に製本をしたものを7月に提出します。学位授与で8月1日から民博。まったくギャップがない。それまでも早い時期から話がありましたので就職のことで悩む必要はなかった。民博の助手に決まったときはまだ31歳だった。就職に関しては本当にラッキーだった。
就職にあたってはモーリスに推薦文を書いてもらいました。推薦文で決まったわけではないと思いますから言いますが、モーリスに推薦文を依頼するとき、日本では推薦文は褒め称えることを意味する、客観的な評価referenceではないと説明しておきました。そのせいか、あとで民博(当時)の伊藤幹治先生(注11)から、欧米人の書いた推薦状を何度も見てきたけど、ブロックの書いたあなたへの推薦文ほどすばらしいものはなかった、と何度も言われました。たぶんモーリスはすごくほめてくれていたのでしょう。
最後にもう一つ付け加えておきます。アメリカの大学だと留学生は本国の調査を勧められると聞いています。まあ実際そうですよね。でも私は当時暴動が何度かあったロンドン南部のブリクストンとか中産階級の典型的な町でもあるミルトン・キーンズなどを勧められました。どちらもことわりましたが、アメリカとの違いとして強調しておきたいと思います。
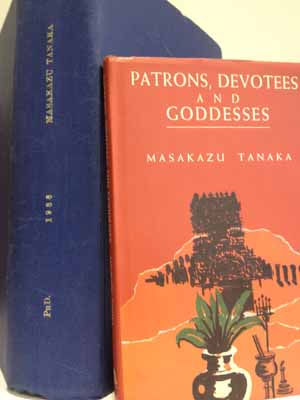
注1:1926-2001、人類学者、霊長類学者。『高崎山のサル』(1954年)で毎日出版文化賞受賞。1984年に人類学のノーベル賞と称されるトーマス・ハックスリー賞を日本人として初めて受賞。日本最初のアフリカ地域研究の機関として、京都大学にアフリカ地域研究センター(現アフリカ地域研究資料センター)を設立。『伊谷純一郎著作集(全6巻)』が平凡社から刊行されている。
注2:ただし、日本と違ってsupervisionという個人指導は制度化されているので指導教員と会う機会は少なくはない。
注3:1998年から2008年までおよそ10年間、100回行われた。詳しくは田中のHPを参照。
注4:主な著書:2000 The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling and SkillRoutledge.
注5:主な著書:2000. The Memory Bank: Money in an unequal world. Profile Books Ltd.
注6:主な著書:1975. Rethinking Symbolism. Cambridge UP., 1985(1979『象徴表現とはなにか』紀伊國屋書店). On Anthropological Knowledge. Cambridge UP., 1996. Explaining Culture. Blackwell.
注7:ただしジョックのときは調査中で不在
注8:Edmund Ronald Leach(1919-1989)。主な著書:1954Political systems of highland Burma: A study of Kachin social structureHarvard University Press.他多数。
注9:1990『人類学再考』思索社.
注10:主な著書:1988The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in MelanesiaUniversity of California Press.
注11:1930-、人類学者・民俗学者。国立民族学博物館名誉教授。2008年に南方熊楠賞受賞。『沖縄の宗教人類学』(1980年)『宗教と社会構造』(1988年)他多数。
注12:1997. Patrons, Devotees and Goddesses: Ritual and Power Among the Tamil Fishermen of Sri Lanka. South Asia Books; 2nd Revised版.
